あさま山荘のひとの一生かくれんぼ
(JARAC様:歌詞は引用の範囲で盗用の意図はございません)
音楽の歴史をひもといていると、時々妙な符合に驚くことがある。
たとえば日吉ミミの「ひとの一生かくれんぼ」という曲がそれだった。
(日吉ミミ「ひとの一生かくれんぼ」)
ひとの一生かくれんぼ
あたしはいつも鬼ばかり
赤い夕陽の裏町で
もういいかい
まあだだよ
寺山修司が作詞したこの曲は、日吉ミミの11枚目のシングルとして1972年(昭和47年)2月25日にリリースされた。
事件マニアな人ならば、この日付を見て気付くことだろう。
そう、この曲は「あさま山荘事件」の最中にリリースされたのだ。
(管理人が2004年に撮影したあさま山荘。この時のことは「あさま山荘、友部正人、そして1972年」に詳しい)
かつてこの国では「革命」が成就できると信じられている時代があった。
その末期...1972年当時、連合赤軍は「人民による人民のための革命」を主張して群馬の山奥にアジトを築いて、警察との「かくれんぼ」を続けていた。
2月16日、「鬼(警察)」は妙義山を中心として大規模な山狩りを開始し、まずは妙義湖の湖畔で「子」...奥沢修一(22)と杉崎ミサ子(24)を「みいつけた」。
翌17日、最高幹部の森恒夫(27)と永田洋子(26)を「みいつけた」鬼は、さらにその包囲網を狭めてゆく。
これはたまらんと、残りのメンバー9名は山越えで長野県の軽井沢へと逃走する。だが2月19日に軽井沢駅で植垣康博(24)、伊藤和子(23)、青砥幹夫(22)、寺林真喜(22)の4人が鬼の虜となってしまった。
残った5人のメンバー(坂口弘、坂東國男、吉野雅邦、加藤倫教、加藤元久)は、軽井沢レイクニュータウンという別荘地にある「さつき山荘」に潜り込むが、異変に気付いた鬼に発見され、「まあだだよ」と銃を乱射しながら逃走する。
そして鬼を振り切ったメンバーは、近くにあった河合楽器の保養所「浅間山荘」への「かくれんぼ」に成功した。管理人の女性を人質となった。
見つからないようにするためには、自分の居場所を鬼に気付かれないようにしなければいけない。
だけど、かくれんぼのルールでは子は鬼に対して「もういいよ」を言うことが義務付けられている。
なぜなら鬼はその声を頼りに子を探しにゆくからだ。
では「もういいよ」を言わない「子」は、どうなってしまうのだろう?
寺山修司が監督と脚本を手がけた映画「田園に死す」はこんなシーンから始まる。
(「田園に死す(1974年)」冒頭のかくれんぼのシーン)
墓場で子供たちがかくれんぼをしている。
鬼の子供は両手で目を覆いながら「もういいかい?」と言う。
子は墓石の裏側に隠れながら「まあだだよ!」と言う。
再び鬼が「もういいかい?」と言うと、
今度は「もういいよ!」と子たちが叫ぶ。
鬼の子供がゆっくりゆっくり両手を開いてゆくと.....墓石の裏側からは、すっかり大人になってしまった子供たちが出てきた。
喪服を来た未亡人、山高帽の紳士、出征する軍人、貴婦人、学生.....
寺山修司は彼の映画、俳句、エッセイなどでしばしば「かくれんぼ」をモチーフにした。
共通して言えるのは、子を見つけられない鬼、あるいは鬼に見つけてもらえない子が、そのまま年老いてゆくというものだ。
「かくれんぼの鬼とかれざるまま老いて誰がさがしにくる村祭」
「かくれんぼ 三つ数えて 冬になる」
幼い頃に母に逃げられ、いまだに母をさがしつづける自分自身のことを(これは彼一流の作り話なのだが)「私はかくれんぼの鬼だ」とも言っている。
「みいつけた」を言われない限り、子は隠れながら年老いてゆくだろう。「もういいよ」を言わない限り、鬼は鬼のまま年老いてゆくだろう。
だから寺山は「かくれんぼは悲しい遊びだ」と書いている。
あさま山荘の「子」たちはそうではなかった。
彼らは雪に残された足跡をたどって山荘に近づいてきた警官にいきなり発砲した。彼らは「もういいよ」を宣言したのだ。
もし「もういいよ」さえ言わなければ....寺山修司風に書くならば彼らは山荘の中で老人となっていったのかもしれない。
炬燵に暖まり、蜜柑をほおばりながら、錆びついたライフル銃を小脇に置いて、革命のプランを練る老人たち。時の流れは急激で、もはやラジオのニュースでは彼らの消息すら報道しない。それが逆に彼らにとっては一番不安だったりする。
時折懐かしい音楽がラジオから流れてくる。耳を傾けると「ひとの一生かくれんぼ」と歌っている。
「もういいかい」「まあだだよ」、歌詞のひとつひとつが心に突き刺さる.....
「ひとの一生かくれんぼ」のリリースから3日後の2月28日、警視庁と長野県警からなる混成部隊はあさま山荘に強行突入した。
警察は殉職者を出しながらも犯人を「みいつけた」。
そして、彼らの取り調べ段階で判明したのは、総括の名の下に同志12名をリンチによって殺害するという「山岳ベース事件」だった。「革命」という大義名分の下に行われた「狂気」に人々は旋律したのだった。
かくれんぼは、これで終わったかのようにみえた。少なくとも一人を除いては.....
1975年8月4日、日本赤軍(連合赤軍とは別組織)がマレーシアのクアランプールにあるアメリカ大使館を襲撃し、大使館員らを人質に立てこもった。
彼らが要求したのは、獄中にいる同士7人の釈放だった。その中にはあさま山荘事件の犯人である坂口弘と坂東國男の名前もあった。
日本政府は「超法規的措置」として7人に出国の意志を確認した。
坂口は出国を拒否し、坂東は出国を希望した。
8月7日14時33分、坂東國男は日航機で日本を出国した。
以来、彼の行方は杳として知れない。
彼の「かくれんぼ」は、今でも続いている。
————————————————————————————————————
さて、この長い記事をまだ読んで下さる奇特な方に、さらに書いてみる。
「ひとの一生かくれんぼ」と同じ2月25日、青い三角定規の2枚目のシングルとして「太陽がくれた季節」がリリースされている。
これは事件発生のの翌日、2月20日から放映開始された「飛び出せ!青春(日本テレビ)」の主題歌だった。
(青い三角定規「太陽がくれた季節」)
君は何を今 見つめているの
若い悲しみに 濡れた眸で
逃げてゆく白い鳩 それとも愛
君も今日からは ぼくらの仲間
とびだそう 青空の下へ
「君」を坂東國男、
「太陽」を日の丸に象徴される日本政府、
「ぼくら」を日本赤軍、
「青春」は海外での世界革命活動とおきかえてみると......坂東の出国を予言しているように思えてならない。
さて、こうなってくると管理人は言葉のゲームを楽しんでいるように思われるだろう。
たぶんそれは事実なんだから仕方がない。
妙義山での山狩りが始める前日の2月15日、平田隆夫とセルスターズが「ハチのムサシは死んだのさ」というシングルをリリースしている。
(平田隆夫とセルスターズ「ハチのムサシは死んだのさ」)
ハチのムサシは死んだのさ
畑の日だまり、土の上
遠い山奥、麦の穂が
キラキラゆれてる午後でしたハチのムサシは向こう見ず
真赤に燃えてるお日様に
試合を挑んで負けたのさ
焼かれて落ちて死んだのさ

「ハチのムサシ」を連合赤軍、
「真っ赤に燃えてるお日様」をこれまた日の丸に象徴される日本政府、
「遠い昔の恋の夢」を人民革命におきかえてみると........そのまま連合赤軍の敗北を暗示しているように思えてならない。
この記事、オチらしいものを書かなければいけないのかもしれないけど、いつもオチをつけないのが「上大岡的音楽生活」なんだから困ったものだ。
少なくとも「歌は世につれ、世は歌につれ」なんて月並みな文句では終わらせたくない。
むしろ「あさま山荘事件」とそれにつながっている一連の事件があまりにも大きくて衝撃的な出来事だったからこそ、音楽の方が磁石に吸い付けられる砂鉄のようにそこに吸着したのだろう。
だから、こんなオチはどうだろう?
「あさま山荘事件」から一週間後、ピンク・フロイドが2度目の来日を果たした。3月6日の東京都体育館を皮切りに全国6か所でのコンサートを行った。
ここでプレイされた新曲の数々は、一年後に「狂気」というアルバムに結実してゆく。



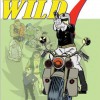
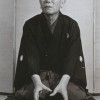

ディスカッション
コメント一覧
「太陽がくれた季節」は今でも歌えるくらい知ってるが、他の2曲はわからないなあ(「ハチのムサシ~」はかろうじて曲名だけ記憶)ほぼ同時期に出ていたということなのに、なんでだろう(^^;)
ていうか、冒頭のジャケット写真、少女マンガのまつ毛をまんま再現してるがごとくの化粧に驚愕だ!(笑)
>羊子さん
そりゃあ羊子さんとは世代が違いますからね(笑)
あさま山荘事件は記憶にありますが、さすがに「ひとの一生かくれんぼ」は僕も覚えていないなぁ。覚えていたら怖いです。
少女マンガのまつ毛が日吉ミミを真似たのか?
日吉ミミが少女マンガのまつ毛を真似たのか?
もしかしたら前者が正しいのかもしれませんよ。
永田洋子には、一度会ったというか、話掛けられたことがあります。と分かったのは、浅間山荘事件の後、彼女についての本を読んでです。
1966年9月、米原子力潜水艦寄港反対運動に横須賀に行った帰り、「大学に持って行ってくれ」と頼まれた某党派の新聞を電車で読んでいると、「あんたは○○なの」と隣の女から聞かれました。
彼女たちは、ちょうどML派から追い出された時で、その5年後に連合赤軍になりますが、彼女はまだ共立薬大生でした。
1970年代中頃、「あの時の不愉快なおばさんは永田洋子だったのか」と思った次第です。
彼女も2011年に病死しました。
さすらい日乗さん
それ、さりげないけど凄い話ですね。実際に永田洋子に会った方が近くにいらっしゃるとは思いもしませんでした。今度お話しをじっくり聞かせて下さい。
「不愉快なおばさん」という日乗さんの直観は、別の人には一種の御し難いカリスマ性として映ったのでしょうね。だからあの一連の悲劇が起きたのだと思いました。